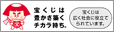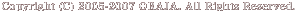HOME > 砂山 とし子
プロフィール
 文久2年(1862年)創業、150年近い歴史を持つ和太鼓店。
文久2年(1862年)創業、150年近い歴史を持つ和太鼓店。
砂山 とし子さんは、その歴史を受け継ぎ、日本で唯一、和太鼓をつくる女性の職人として注目された和太鼓職人であった。
太鼓づくりの一貫工程の中でも、特に音の良し悪しに影響を及ぼす革のなめし方、張り方の技術が見事で、多くの名品を生み出してきたが平成16年に他界。
その伝統のある名人芸は、20年以上も一緒に仕事をしてきた孫の敦(あつし)さん(43)に受け継がれている。




(砂山 とし子は、正しくは上記のように書く)
| 産業分類 | 伝統的産業 |
|---|---|
| 認定年度(平成) | 平成9年 |
| マイスターの分野 | 太鼓 |
| 氏名 | 砂山 とし子 |
| ふりがな | すなやま としこ |
| 性別 | 女 |
| 生年月日 | 大正4年10月8日(平成16年3月 88歳で他界) |
| 住所 | 上越市北本町4丁目 |
砂山さんの軌跡
150年の歴史を持つ砂山太鼓店

太鼓づくりはまず、材料となるケヤキや革の選定から始まる。ケヤキは東頸城の山中のものを使った。年数をかけて大きくなった木を約3年間乾燥、回りを削り中心に近い部分を胴にした。革は雌牛が最高とされた。牛一頭のうち、腹や尻の部分を使い分けた。革の仲買人の経験もあり、選定には厳しい目が光った。
革張りは一番神経を集中させる工程だ。水を吸わせ、伸ばす過程で「なじみを出しながら」4日かけて乾燥させていく。わずかな加減で音色が変わるため、少しずつ引っ張り、最後に鋲(びょう)で止める。乾いて澄んだ音が特徴の締め太鼓の場合、両面に張られた革に麻縄を渡して締め上げることで、革の張り具合を調整していく。力技も要求され、演奏者が求める音を出せるかが決まる大事な瞬間だ。 太鼓づくりを引き継ぐ孫の敦さん

「革の特徴をつかむ、見極めることが大事」。「先代がよく口にしていた」と敦さんがいつも心に刻んでいる大切な言葉だ。同じようになめした革でも、繊維質の状態によって強度に優れたり、しなやかであったりするからだ。
「先代は厳しかったが、自分でやってみないと分かったことが生まれてこない。仕事の経験をたくさん積んで、コツをつかめと、自主性を重んじてくれた」と言葉一つ一つをかみしめ、今日も革の張替えや新規の太鼓づくりに心を込めて取り組んでいる。

太鼓づくりはまず、材料となるケヤキや革の選定から始まる。ケヤキは東頸城の山中のものを使った。年数をかけて大きくなった木を約3年間乾燥、回りを削り中心に近い部分を胴にした。革は雌牛が最高とされた。牛一頭のうち、腹や尻の部分を使い分けた。革の仲買人の経験もあり、選定には厳しい目が光った。
革張りは一番神経を集中させる工程だ。水を吸わせ、伸ばす過程で「なじみを出しながら」4日かけて乾燥させていく。わずかな加減で音色が変わるため、少しずつ引っ張り、最後に鋲(びょう)で止める。乾いて澄んだ音が特徴の締め太鼓の場合、両面に張られた革に麻縄を渡して締め上げることで、革の張り具合を調整していく。力技も要求され、演奏者が求める音を出せるかが決まる大事な瞬間だ。 太鼓づくりを引き継ぐ孫の敦さん

「革の特徴をつかむ、見極めることが大事」。「先代がよく口にしていた」と敦さんがいつも心に刻んでいる大切な言葉だ。同じようになめした革でも、繊維質の状態によって強度に優れたり、しなやかであったりするからだ。
「先代は厳しかったが、自分でやってみないと分かったことが生まれてこない。仕事の経験をたくさん積んで、コツをつかめと、自主性を重んじてくれた」と言葉一つ一つをかみしめ、今日も革の張替えや新規の太鼓づくりに心を込めて取り組んでいる。

 このページのTOPへ
このページのTOPへ